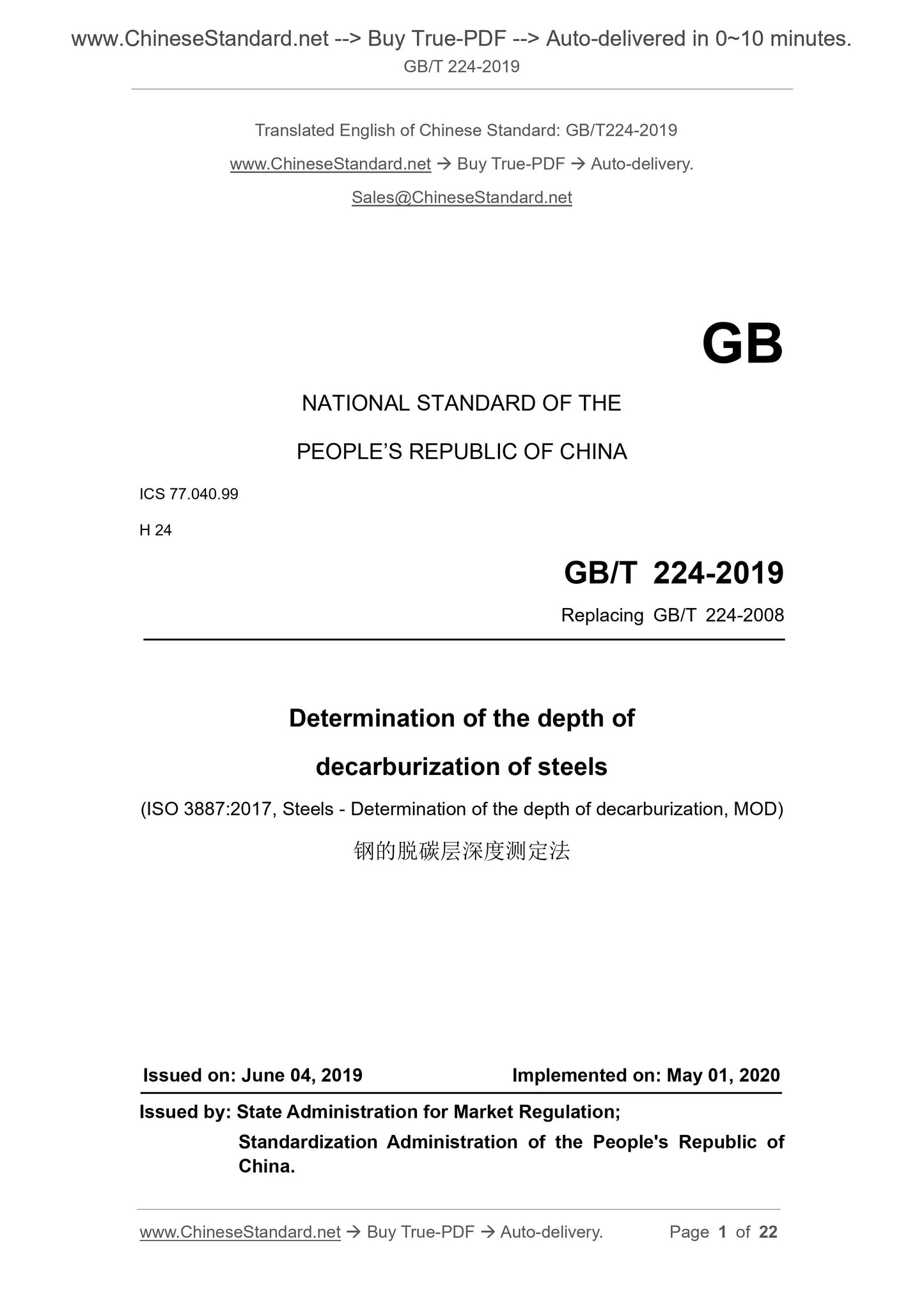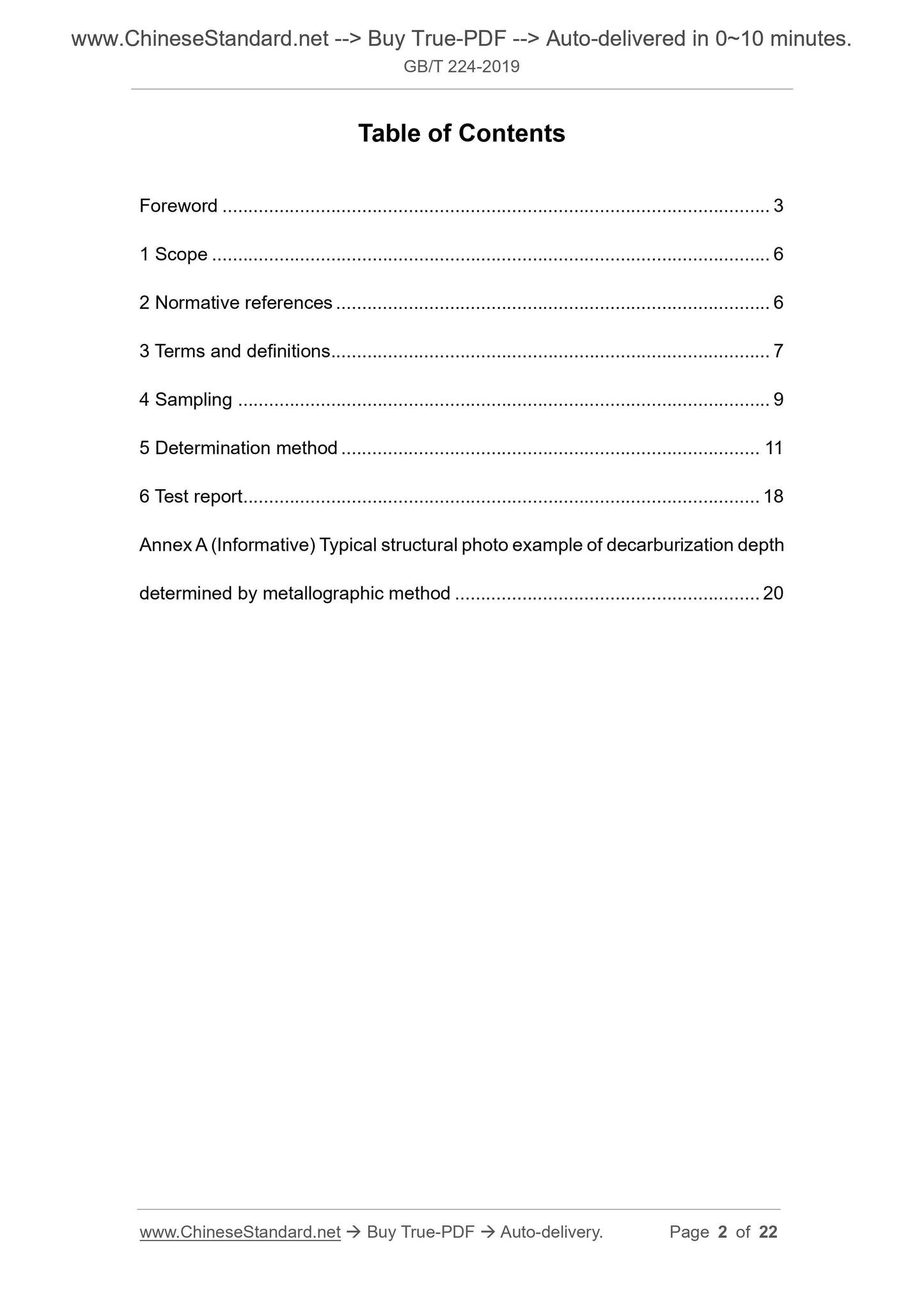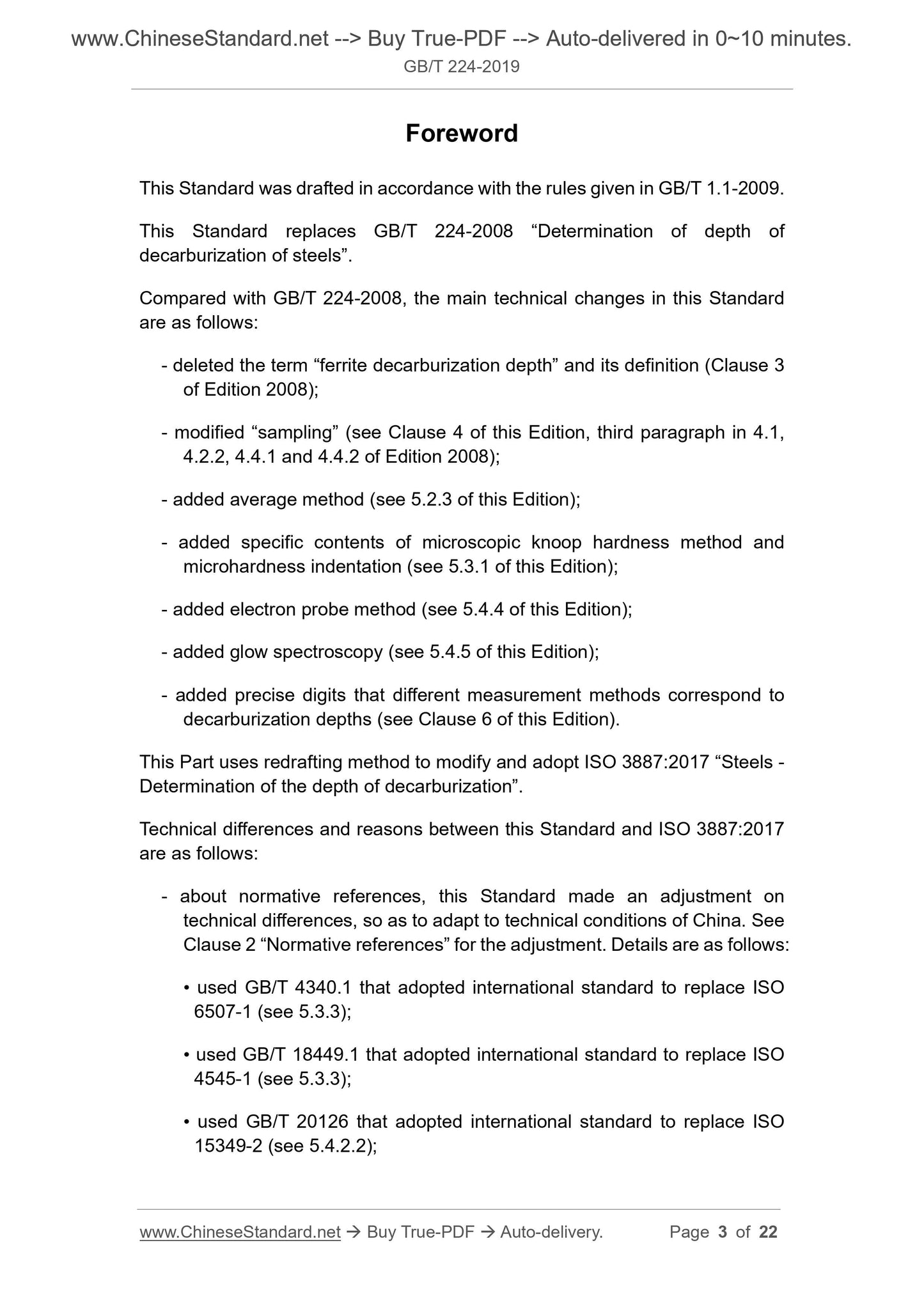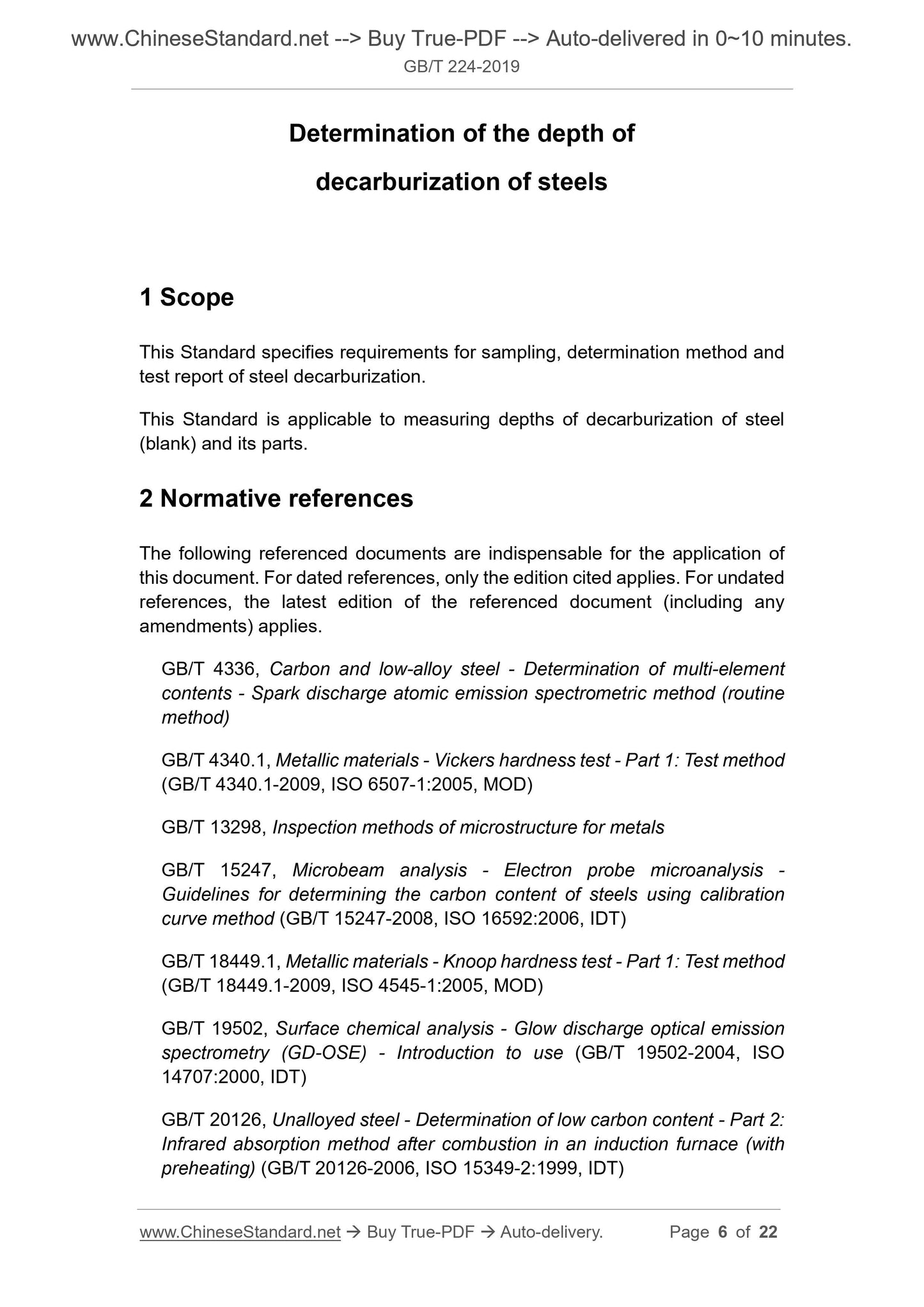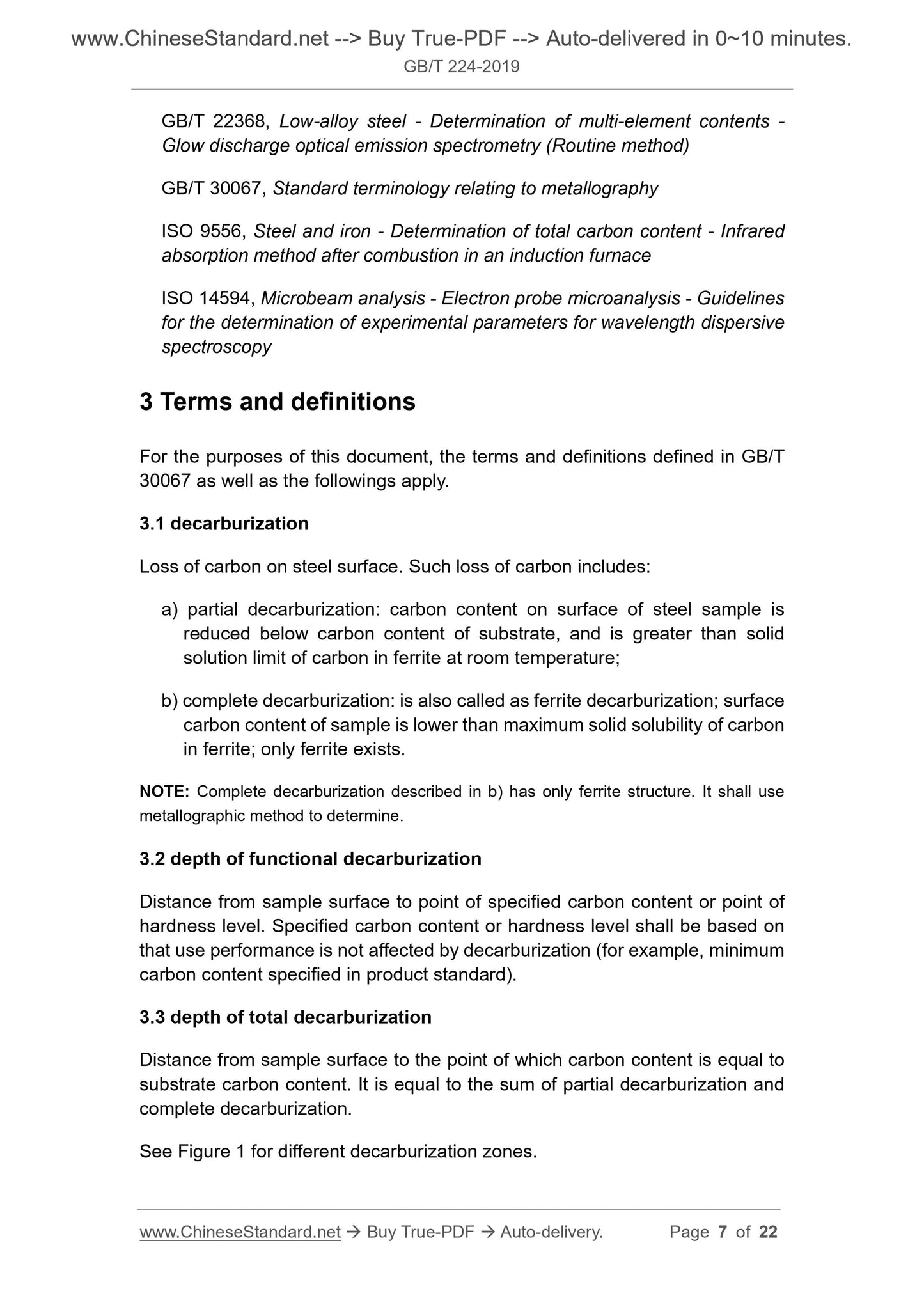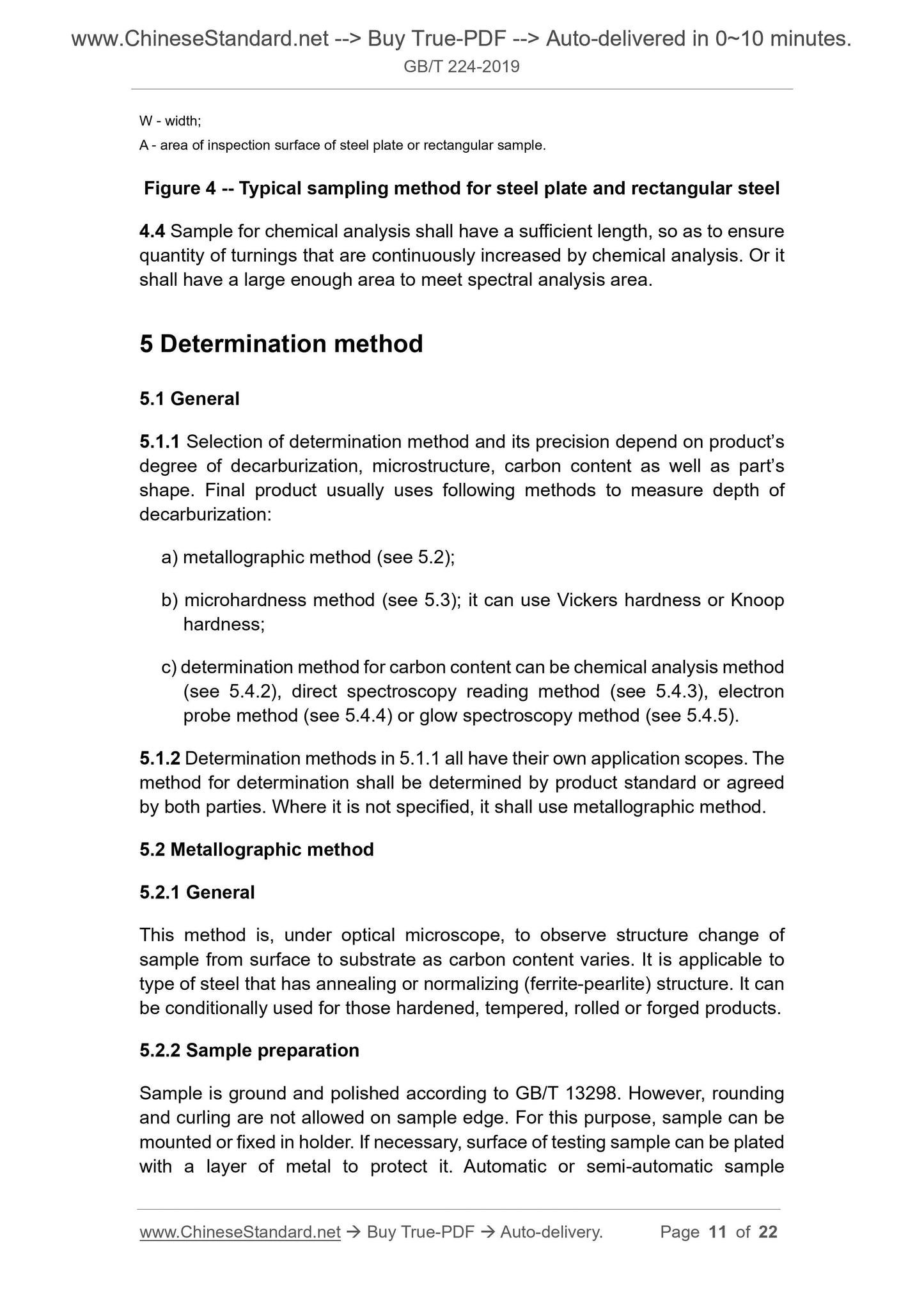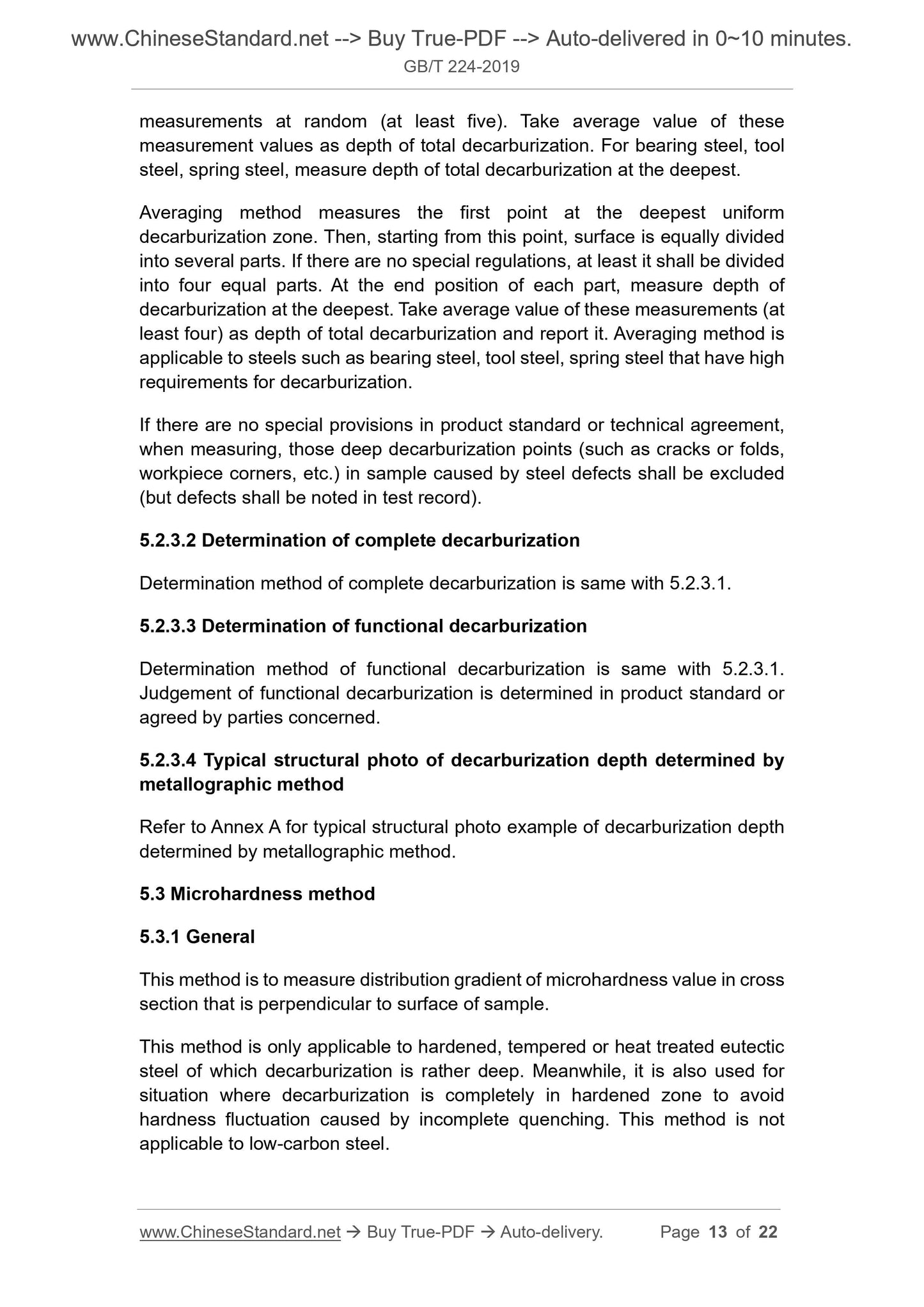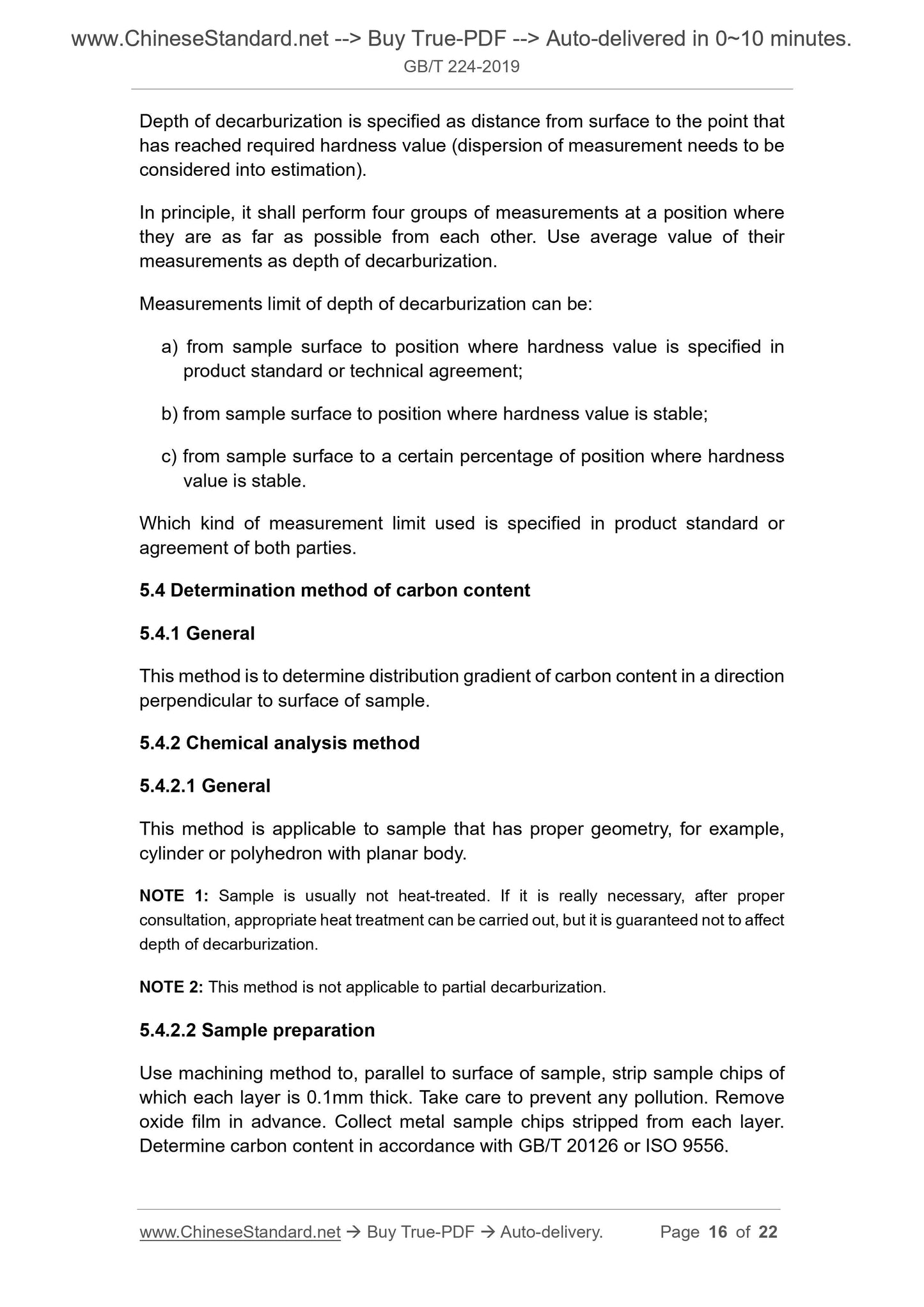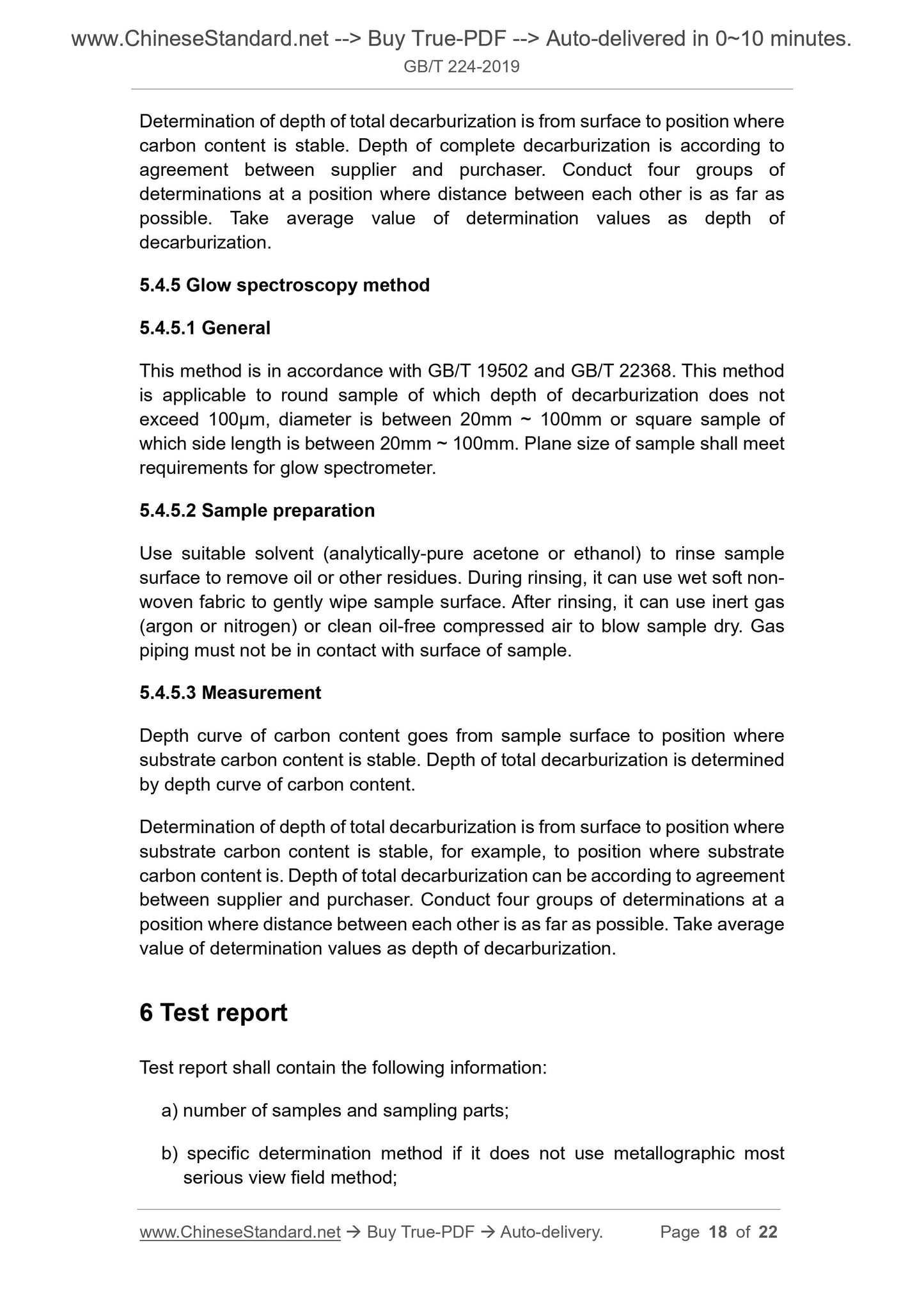1
/
の
9
PayPal, credit cards. Download editable-PDF and invoice in 1 second!
GB/T 224-2019 英語 PDF (GBT224-2019)
GB/T 224-2019 英語 PDF (GBT224-2019)
通常価格
$145.00 USD
通常価格
セール価格
$145.00 USD
単価
/
あたり
配送料はチェックアウト時に計算されます。
受取状況を読み込めませんでした
配信: 3 秒。真の PDF + 請求書をダウンロードしてください。
1分で見積もりを取得: GB/T 224-2019をクリック
過去のバージョン: GB/T 224-2019
True-PDF をプレビュー(空白の場合は再読み込み/スクロール)
GB/T 224-2019: 鋼の脱炭深さの測定
GB/T 224-2019
国家標準の
中華人民共和国
ICS77.040.99
H 24
GB/T 224-2008 の置き換え
深さの決定
鋼の脱炭
(ISO 3887:2017、鋼 - 脱炭深度の測定、MOD)
発行日: 2019年6月4日
実施日: 2020年5月1日
発行元:国家市場監督管理総局
中華人民共和国標準化管理局
中国。
目次
序文…3
1 範囲 ... 6
2 規範的参照 ... 6
3 用語と定義 ... 7
4 サンプリング ... 9
5 判定方法 ... 11
6 テストレポート ... 18
付録A(参考)脱炭深度の典型的な組織写真例
金属組織学的方法により決定...20
序文
この規格は、GB/T 1.1-2009 に規定された規則に従って作成されました。
この規格は、GB/T 224-2008「
「鋼の脱炭」。
GB/T 224-2008と比較すると、この規格の主な技術的変更点は
は次のとおりです。
- 「フェライト脱炭深さ」という用語とその定義を削除(第3項)
2008年版);
- 修正された「サンプリング」(本版の第4項、4.1の第3段落を参照)
2008年版の4.2.2、4.4.1、4.4.2);
- 平均法を追加(本版の5.2.3を参照)。
- 顕微鏡的ヌープ硬度法の具体的な内容を追加し、
微小硬度の押込み(本版の5.3.1を参照)
- 電子プローブ法を追加(本版の5.4.4を参照)。
- グロー分光法を追加(この版の5.4.5を参照)。
- さまざまな測定方法に対応する正確な数字を追加しました
脱炭深度(本版の第6項を参照)。
このパートでは、ISO 3887:2017「鋼材 -
「脱炭深度の決定」。
この規格と ISO 3887:2017 の技術的な相違点とその理由
は次のとおりです。
- 規範的参照については、この規格では、
中国の技術的条件に適応するために、技術的な違いがあります。
調整のための第2項「規範的参照」。詳細は次のとおりです。
• ISOに代わる国際標準規格であるGB/T 4340.1を採用
6507-1(5.3.3参照)
• ISOに代わる国際標準規格であるGB/T 18449.1を採用
4545-1(5.3.3参照)
• ISOに代わる国際標準規格であるGB/T 20126を採用
15349-2(5.4.2.2参照)
深さの決定
鋼の脱炭
1 範囲
この規格は、サンプリング、測定方法、および
鋼の脱炭に関する試験報告書。
この規格は鋼の脱炭深さの測定に適用される。
(空白)とその部分。
2 規範的参照
以下の参照文書は、
この文書。日付のある参考文献については、引用された版のみが適用されます。日付のない参考文献については、
参考文献、参照文書の最新版(
(改正)が適用されます。
GB/T 4336、炭素鋼および低合金鋼 - 多元素分析
内容 - スパーク放電発光分光法(ルーチン
方法)
GB/T 4340.1、金属材料 - ビッカース硬度試験 - パート 1: 試験方法
(GB/T 4340.1-2009、ISO 6507-1:2005、MOD)
GB/T 13298、金属の微細構造の検査方法
GB/T 15247、マイクロビーム分析 - 電子プローブマイクロ分析 -
校正法を用いた鋼の炭素含有量の測定ガイドライン
曲線法(GB/T 15247-2008、ISO 16592:2006、IDT)
GB/T 18449.1、金属材料 - ヌープ硬度試験 - パート 1: 試験方法
(GB/T 18449.1-2009、ISO 4545-1:2005、MOD)
GB/T 19502、表面化学分析 - グロー放電発光
分光法(GD-OSE) - 使用方法の紹介(GB/T 19502-2004、ISO
14707:2000、IDT)
GB/T 20126、非合金鋼 - 低炭素含有量の測定 - パート2:
誘導炉燃焼後の赤外線吸収法(
予熱)(GB/T 20126-2006、ISO 15349-2:1999、IDT)
GB/T 22368、低合金鋼 - 多元素含有量の測定 -
グロー放電発光分光分析法(通常法)
GB/T 30067、金属組織学に関する標準用語
ISO 9556、鉄鋼 - 総炭素含有量の測定 - 赤外線
誘導炉での燃焼後の吸収法
ISO 14594、マイクロビーム分析 - 電子プローブマイクロ分析 - ガイドライン
波長分散型測定の実験パラメータの決定
分光法
3 用語と定義
この文書では、GB/Tで定義された用語と定義は、
30067 および以下が適用されます。
3.1 脱炭
鋼鉄表面の炭素損失。このような炭素損失には以下が含まれます。
a) 部分脱炭:鋼サンプルの表面の炭素含有量は
基質の炭素含有量以下に減少し、固体よりも大きい
室温でのフェライト中の炭素の固溶限界。
b) 完全脱炭:フェライト脱炭とも呼ばれる。表面
サンプルの炭素含有量は炭素の最大固溶度よりも低い
フェライトにはフェライトのみが存在する。
注:b)で説明した完全な脱炭はフェライト組織のみである。
金属組織学的方法で決定する。
3.2 機能的脱炭の深さ
サンプル表面から指定された炭素含有量の点または
硬度レベル。指定された炭素含有量または硬度レベルは、
使用性能が脱炭化の影響を受けないこと(例えば、最小
製品規格に規定された炭素含有量。
3.3 総脱炭深度
サンプル表面から炭素含有量が等しい点までの距離
基質炭素含有量。これは部分脱炭と
完全な脱炭。
さまざまな脱炭ゾーンについては図 1 を参照してください。
W - 幅;
A - 鋼板または長方形サンプルの検査表面の領域。
図4 - 鋼板および長方形鋼の一般的なサンプリング方法
4.4 化学分析のためのサンプルは、以下のことを確実にするために十分な長さを持つものとする。
化学分析によって継続的に増加する旋削量。またはそれは
スペクトル分析領域を満たすのに十分な大きさの領域を有するものとする。
5 判定方法
5.1 一般事項
5.1.1 測定方法の選択とその精度は製品の
脱炭度、微細構造、炭素含有量、および部品の
形状。最終製品は通常、以下の方法で深さを測定します。
脱炭:
a) 金属組織学的方法(5.2参照)
b) 微小硬度法(5.3参照)ビッカース硬度またはヌープ硬度を使用することができる。
硬度;
c) 炭素含有量の測定方法は化学分析法である。
(5.4.2参照)、直接分光法(5.4.3参照)、電子
プローブ法(5.4.4参照)またはグロー分光法(5.4.5参照)のいずれかである。
5.1.2 5.1.1の判定方法にはそれぞれ適用範囲があります。
決定方法は製品規格または合意によって決定される。
両者により行う。特に指定がない場合は、金属組織学的方法を使用する。
5.2 金属組織学的方法
5.2.1 一般事項
この方法は、光学顕微鏡下で構造変化を観察するものである。
炭素含有量が変化するため、表面から基質までサンプルを採取する。
焼きなましまたは焼きならし(フェライト・パーライト)構造を持つ鋼の一種。
条件付きで、硬化、焼き入れ、圧延、鍛造された製品に使用されます。
5.2.2 サンプルの準備
1分で見積もりを取得: GB/T 224-2019をクリック
過去のバージョン: GB/T 224-2019
True-PDF をプレビュー(空白の場合は再読み込み/スクロール)
GB/T 224-2019: 鋼の脱炭深さの測定
GB/T 224-2019
国家標準の
中華人民共和国
ICS77.040.99
H 24
GB/T 224-2008 の置き換え
深さの決定
鋼の脱炭
(ISO 3887:2017、鋼 - 脱炭深度の測定、MOD)
発行日: 2019年6月4日
実施日: 2020年5月1日
発行元:国家市場監督管理総局
中華人民共和国標準化管理局
中国。
目次
序文…3
1 範囲 ... 6
2 規範的参照 ... 6
3 用語と定義 ... 7
4 サンプリング ... 9
5 判定方法 ... 11
6 テストレポート ... 18
付録A(参考)脱炭深度の典型的な組織写真例
金属組織学的方法により決定...20
序文
この規格は、GB/T 1.1-2009 に規定された規則に従って作成されました。
この規格は、GB/T 224-2008「
「鋼の脱炭」。
GB/T 224-2008と比較すると、この規格の主な技術的変更点は
は次のとおりです。
- 「フェライト脱炭深さ」という用語とその定義を削除(第3項)
2008年版);
- 修正された「サンプリング」(本版の第4項、4.1の第3段落を参照)
2008年版の4.2.2、4.4.1、4.4.2);
- 平均法を追加(本版の5.2.3を参照)。
- 顕微鏡的ヌープ硬度法の具体的な内容を追加し、
微小硬度の押込み(本版の5.3.1を参照)
- 電子プローブ法を追加(本版の5.4.4を参照)。
- グロー分光法を追加(この版の5.4.5を参照)。
- さまざまな測定方法に対応する正確な数字を追加しました
脱炭深度(本版の第6項を参照)。
このパートでは、ISO 3887:2017「鋼材 -
「脱炭深度の決定」。
この規格と ISO 3887:2017 の技術的な相違点とその理由
は次のとおりです。
- 規範的参照については、この規格では、
中国の技術的条件に適応するために、技術的な違いがあります。
調整のための第2項「規範的参照」。詳細は次のとおりです。
• ISOに代わる国際標準規格であるGB/T 4340.1を採用
6507-1(5.3.3参照)
• ISOに代わる国際標準規格であるGB/T 18449.1を採用
4545-1(5.3.3参照)
• ISOに代わる国際標準規格であるGB/T 20126を採用
15349-2(5.4.2.2参照)
深さの決定
鋼の脱炭
1 範囲
この規格は、サンプリング、測定方法、および
鋼の脱炭に関する試験報告書。
この規格は鋼の脱炭深さの測定に適用される。
(空白)とその部分。
2 規範的参照
以下の参照文書は、
この文書。日付のある参考文献については、引用された版のみが適用されます。日付のない参考文献については、
参考文献、参照文書の最新版(
(改正)が適用されます。
GB/T 4336、炭素鋼および低合金鋼 - 多元素分析
内容 - スパーク放電発光分光法(ルーチン
方法)
GB/T 4340.1、金属材料 - ビッカース硬度試験 - パート 1: 試験方法
(GB/T 4340.1-2009、ISO 6507-1:2005、MOD)
GB/T 13298、金属の微細構造の検査方法
GB/T 15247、マイクロビーム分析 - 電子プローブマイクロ分析 -
校正法を用いた鋼の炭素含有量の測定ガイドライン
曲線法(GB/T 15247-2008、ISO 16592:2006、IDT)
GB/T 18449.1、金属材料 - ヌープ硬度試験 - パート 1: 試験方法
(GB/T 18449.1-2009、ISO 4545-1:2005、MOD)
GB/T 19502、表面化学分析 - グロー放電発光
分光法(GD-OSE) - 使用方法の紹介(GB/T 19502-2004、ISO
14707:2000、IDT)
GB/T 20126、非合金鋼 - 低炭素含有量の測定 - パート2:
誘導炉燃焼後の赤外線吸収法(
予熱)(GB/T 20126-2006、ISO 15349-2:1999、IDT)
GB/T 22368、低合金鋼 - 多元素含有量の測定 -
グロー放電発光分光分析法(通常法)
GB/T 30067、金属組織学に関する標準用語
ISO 9556、鉄鋼 - 総炭素含有量の測定 - 赤外線
誘導炉での燃焼後の吸収法
ISO 14594、マイクロビーム分析 - 電子プローブマイクロ分析 - ガイドライン
波長分散型測定の実験パラメータの決定
分光法
3 用語と定義
この文書では、GB/Tで定義された用語と定義は、
30067 および以下が適用されます。
3.1 脱炭
鋼鉄表面の炭素損失。このような炭素損失には以下が含まれます。
a) 部分脱炭:鋼サンプルの表面の炭素含有量は
基質の炭素含有量以下に減少し、固体よりも大きい
室温でのフェライト中の炭素の固溶限界。
b) 完全脱炭:フェライト脱炭とも呼ばれる。表面
サンプルの炭素含有量は炭素の最大固溶度よりも低い
フェライトにはフェライトのみが存在する。
注:b)で説明した完全な脱炭はフェライト組織のみである。
金属組織学的方法で決定する。
3.2 機能的脱炭の深さ
サンプル表面から指定された炭素含有量の点または
硬度レベル。指定された炭素含有量または硬度レベルは、
使用性能が脱炭化の影響を受けないこと(例えば、最小
製品規格に規定された炭素含有量。
3.3 総脱炭深度
サンプル表面から炭素含有量が等しい点までの距離
基質炭素含有量。これは部分脱炭と
完全な脱炭。
さまざまな脱炭ゾーンについては図 1 を参照してください。
W - 幅;
A - 鋼板または長方形サンプルの検査表面の領域。
図4 - 鋼板および長方形鋼の一般的なサンプリング方法
4.4 化学分析のためのサンプルは、以下のことを確実にするために十分な長さを持つものとする。
化学分析によって継続的に増加する旋削量。またはそれは
スペクトル分析領域を満たすのに十分な大きさの領域を有するものとする。
5 判定方法
5.1 一般事項
5.1.1 測定方法の選択とその精度は製品の
脱炭度、微細構造、炭素含有量、および部品の
形状。最終製品は通常、以下の方法で深さを測定します。
脱炭:
a) 金属組織学的方法(5.2参照)
b) 微小硬度法(5.3参照)ビッカース硬度またはヌープ硬度を使用することができる。
硬度;
c) 炭素含有量の測定方法は化学分析法である。
(5.4.2参照)、直接分光法(5.4.3参照)、電子
プローブ法(5.4.4参照)またはグロー分光法(5.4.5参照)のいずれかである。
5.1.2 5.1.1の判定方法にはそれぞれ適用範囲があります。
決定方法は製品規格または合意によって決定される。
両者により行う。特に指定がない場合は、金属組織学的方法を使用する。
5.2 金属組織学的方法
5.2.1 一般事項
この方法は、光学顕微鏡下で構造変化を観察するものである。
炭素含有量が変化するため、表面から基質までサンプルを採取する。
焼きなましまたは焼きならし(フェライト・パーライト)構造を持つ鋼の一種。
条件付きで、硬化、焼き入れ、圧延、鍛造された製品に使用されます。
5.2.2 サンプルの準備
共有